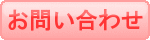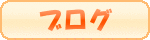今回は、前記事で挙げたポイントの(1)「過去問での学習」について説明していきます。
過去問を使用する学習は、基本的に“志望校”の過去問は使用しません。志望校の過去問をやりたい、やらせたいという気持ちはわかりますが、ここはぐっとこらえていただきます。志望校の過去問をやっても、基本的に良いことはありません。やり始めの段階では「未学習、未習熟」など、まだまだ点数化という部分で至らない点が多くあるため、思ったような結果にならず、落胆し、不安が大きくなる可能性があるからです。また、模試が機能しないことを考えれば、効果測定のための好材料を無為に消費することになるからです。
「学習対象の過去問の選定」
まず、過去問は難易度に関係なく、基本に忠実な学校の問題を使用します(具体的な学校名に関しては企業秘密とさせていただきます)。過去問で“学習”をするとき、どの学校をチョイスするかで結果が大きく変わってきます。 たとえば、以下のようなケースが見られる場合、それぞれの対応をしていきます。
①選定した過去問において極端に点数が取れない。
②あるレベルまでは点数が取れるが、そこから伸びず志望校まで届かない
③時間をかければ点数が取れるが、制限時間内だと点数が大きく下がる。
上記の問題が確認されたとき、
①の場合、状況に合わせた過去問の選定し直し
②の場合、過去問で出来ていない問題を抽出し、関連する基本事項の徹底演習を行う
③の場合、点数が取れているので“適切な問題抽出”と反復学習
によって解決していきます。
こう書くと、当たり前と思われるかもしれません。しかし、①~③のどれも簡単ではありません。簡単でない理由は、
①について
現時点までの「生徒の特性」「過去問の解答」を相互分析して、適切な過去問を選定する必要があるからです。
②について
出来ていない問題の「どの部分を」「どのように」徹底演習させれば効果的かを明確に分かっていなければ、間違った問題の解き直しで終わり原因解決に結びつかないからです。
③について
点数が取れていて時間がかかるのであれば、「習熟すべき対象」に時間をかけていないからです。テストのときには制限時間があります。往々にして、遅いから急がせる。これは、逆効果です。「短い制限時間が課せられている」のはテスト時だけです。つまり、解答時間を短くするために、「長い時間をかけて習熟」することが大切になります。この習熟対象は②と同様です。的確な習熟対象に時間をかけていくことが大切です。習熟対象を見誤ると、長い時間をかける以上大きな損失になることは言うまでもありません。
このように「過去問での学習」は、とても管理が難しいです。しかし、上手く運用すると効果が非常に大きいので、丁寧に慎重に行ってまいります。
ここまで書きましたが、あくまでも過去問学習をする前に、きちんとした学習をしてきたことが前提です。この前提が無いと過去問をどのように行っても成果はあがりません。基本学習の抜けがある場合は、過去問の開始が遅れますが、我慢をして一歩ずつ歩を進めてもらいます。 次回はイントロダクションで挙げたポイント(2)「時間管理」について書かせていただきます。