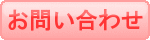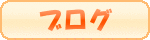授業実施日 6月27日
科目 国語
学年 5年
5年から6年の中盤にかけて、「諺(ことわざ)」の習熟に努めてもらっています。この習熟に、国語の授業時間の半分を使っています。通常であれば、ことわざを単純に覚えるならば、ここまで時間をかける必要はありません。しかし、ONEでは明確な意図があり「諺」の授業を行っています。
通常、諺の授業では「対象の諺の意味(言いたいこと)を知り覚えること」が目的となります。言い方を変えると、単純暗記をすることが目的となります。確かに、受験では諺の意味が問われることがあるため、覚えてもらうことには一定の価値があります。
しかし、ONEでは諺の“習熟”を授業で行います。つまり、単純暗記を目的としていません。諺を使ってどのように授業を進行しているか説明させて頂きます。
授業では繰り返し、「もとの諺」を翻訳し、「諺の意味(言いたいこと)」まで読解することを行っています。これにより、1文を読めるようになっていきます。ここで重要なのは、どのように翻訳し読解するかですが、細かな説明は伏せさせていただきます。
この1文が読めることは長文読解において基本となります。長文は、極論すると「1文の集合体」です。そもそも、長文読解に必要なものは、
①1文を読めること
②その文に必要なリテラシー(知識)
の2点です。この2点を習熟すれば、文脈は取れるようになります。中学受験では、長文読解の配点比率が多いことを考えると、どうせ覚えなければいけない諺を最大限利用することがONEでは効率的だと考えています。また、どの科目でも文章の意図を汲みとれなければ解答できません。1文を読解できるということが受験において、とても重要であるかはお分かりいただけるかと思います。
長文を読めるようになる頭を作るための一つの手段として諺を扱っているので、多くの時間を費やしています。諺という1行文章読解に価値を見出してもらえたらと思います。繰り返しになりますが、ONEでは丁寧に時間をかけてまいります。
(担当 伯母)