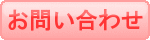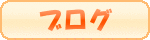5年生の社会の授業の目的は、簡単に言ってしまえば「覚えることを覚える」ということです。
・自分に合った覚えるための方法を見つける。
・覚えたかどうかの判断を確実にできるようになる。
・締め切りまでに覚えることを意識する。
こういったことができるようになることが目標です。極端に言えば,これができるようになれば、社会科の知識それ自体は忘れてしまっても問題はありません。必要な時期に再度覚え直せばよいからです。
ここからしばらくは地理の内容を扱っていきますが、当面の間は2つの方向からアプローチをしていきます。
(1)都道府県・都道府県庁所在地のテスト
これから地理の学習をしていくと、都道府県の名前が頻繁に登場します。今後の学習を進めていく上で、都道府県の名前と場所に関する知識がすぐに出てこないと理解が困難になります。都道府県に関しては、しばらく授業で扱わなくなっても、当たり前の常識として定着しているという状態を目標にしています。したがって、都道府県テストでは「思い出しながら答えを書く」というレベルではなく、ごく短い時間の中で、すべての都道府県、都道府県庁所在地を完璧に答えられるようにしてもらいます。4年生のときにも覚える練習をしていたので、すでに完璧になっている方もいらっしゃいますが、
思い出しながら答えを書いているような状態では、数週間も放っておいたら忘れてしまいます。「ええと、ここは何だったっけ?」といった具合に思い出しながら、答えを書いているのではまずいことを認識してもらって,繰り返し練習し、当たり前のものとして扱えるレベルの知識にしてもらいます。
(2)授業の復習テスト
毎回、テーマを決めて、新しい知識を学んでいきます。現在は「稲作」について扱っています。前回は「コメの生産に適した場所の特徴、生産量の多い都道府県」について、今回は「食糧管理制度と減反政策」について説明をし、記憶をしてもらった後で確認プリントをやってもらいました。いざ確認をすると、覚えたと思っていたものが「あれ、何だったっけ」「さっきまで覚えていたのに」といった状況になることは珍しくありません。こういう経験を繰り返していくうちに、覚えたかどうかの判断を徐々にしっかりとできるようになっていくことが重要です。
学習した内容については、翌週の授業でテストを行います。最初はできないことも多いと思います。テストができない場合には、できない理由があります。授業において、そのできなかった理由にアプローチをしていきます。