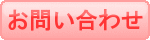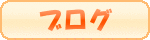過去問演習において、「履修範囲の基本問題」を「九九」のようにスムーズに扱えるようになっていることはとても大切です。このポイントを浮き彫りにし対策していくことが過去問演習の大きな目的なのです。ただし、この場合にも使用された過去問が明確な意図をもって選択されていないと、効果はほぼ無いと言っても過言ではありません。やみくもに過去問を繰り返しても、制限時間内で解き終わることも合格点に達することも難しくなっていきます。
「九九」となった基本問題はとても大切な役目を果たしてくれます。難度の高い問題とは、基本問題の組み合わせです。難しい問題を解くとは、問いの中の基本に気が付き、分解・咀嚼できることを意味します。
「ある時点で難度が高いと感じた問題」は、その基本概念が未習熟だから難度が高いと感じるのです。難度が高い問題がよく習熟された状態(九九)にまで達すると、今度は「今まで難しいと感じていた問題」が基本概念として働くようになり、次の段階の難度の高い問題に利用されていきます。この繰り返しによって、より高難度の問題に取り掛かれるようになるのです。
これは、勉強ができるようになっていくプロセスとして、至極当たり前と感じる方もいらっしゃると思いますが、重要なのは具体的にどのようにすれば、「それを実現できるのか」だと思います。
このためには
・取り組もうとしている問題にアプローチするための「基本概念の抜け」を見極めること
・それに対処するための適切な問題を選択すること
が必要となります。
どちらにも、経験と知識が必要となります。概念としては単純でも、具体的な方法・対策となると単純でなく手間と時間がかかるのです。過去問選択、的確な演習問題の選択は非常に重要なテーマとなります。 次回は②「未履修範囲でも一般的な常識問題に対処できているか」・③「真剣に過去問に取り組めているか」を説明させていただきます。