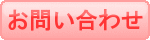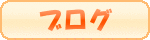「国語の記述について」の第2回目の記事になります。
1回目の記事はこちら→国語の記述について(1) -「てにをは」の使い方―
ONEでは、4年生が記述した答えについては、原則的にマル・バツをあまりつけません。
全くつけないというわけではありませんが、テストのようにシビアにつけるということはしません。
大人から見たら至らない箇所が多々ある答えでもマルをつけることがありますし、明らかな間違いでもバツはつけず、たくさん書いてきたことを評価するコメントをすることもあります。
答えの足りないところに赤ペンで加筆修正をする、いわゆる添削指導のようなことはしていません。どうして、このような指導をしているのかということについて、書かせていただきます。
記述対策と言えば「添削」というのが定番になっています。
生徒の書いた答案が真っ赤になって帰ってくる。それを読んで、自分の答えの足りなかったポイントなどを確認し、それを踏まえてもう一度書いてみたりする……というのが一般的な方法でしょう。
この添削は、すべての生徒にとって意味のある学習になるかというと、必ずしもそうとは言い切れないと考えています。
国語が得意で、記述についても苦にしないという生徒にとっては、添削で指摘されたポイントを単に「その問題のポイント解説」として読むだけでなく、「一般的な注意点」として理解することが可能でしょう。
同じ文章、同じ問題が受験で出るという可能性はほぼゼロなので、添削で指摘されたことを「一般的な注意点」として理解しなければ、次につながる形にはなりません。これができるのは、相当に国語が得意な生徒に限られるでしょう。
実は多くの生徒は、その問題の解説としてしか添削を読むことができません。
なので、添削が特効薬になるという可能性は高くはありません。もっとも特に添削をすることにマイナスがあるということはありませんし、毎週毎週繰り返していればそこから何かつかみ取れるケースもあるでしょう。
国語が苦手な生徒や、まだ記述すること自体に不慣れな生徒の場合は注意が必要です。
生徒が記述すること自体に苦手意識、できればやりたくないという思いを持っているケースでは「まずは書いてみる」ということが重要です。まとめ方が上手いかどうか、文法的なミスがないかといったことは気にせず、書かなければ前に進めません。
この段階の生徒が時間をかけてまとめ上げた答案を真っ赤に添削することは、「やっぱり書いても点にならない」・「自分は記述が苦手」という思いを強くしてしまう結果につながるリスクがあります。きちんと記述をしたことについてプラスの評価をされることで、書くことに対する心理的な抵抗は少しずつ軽くなっていきます。
内容的な修正、文法的な誤りの指摘などは、ある程度書くことが当たり前になってからにしないと、「うまく書けないから書きたくない、書かない」という姿勢が固まってしまいます。
テストの度に記述問題が空欄になるというような生徒の場合は、添削はむしろ危険だと考えます。
4年生の段階では、多くのお子様は記述することに対して不慣れです。
この段階で「書くことに対するマイナス感情」を持たせてしまうことは避けなければいけません
。この段階では書いた答えに細かい注文をつけず、書いてきた努力を認め、書くことに対する抵抗を少しでも減らしていくということを考えています。
記述の答えの扱いは本当は学年で決まるわけではなく、お子様の到達段階によって変わります。
当たり前に書けるようになったら、徐々に要求値を上げていきます。得意な生徒と苦手な生徒では、当然要求されることが変わってきますので、同じ答えを書いたのに、ある生徒はマルになり、ある生徒はバツになる……といったこともあります。